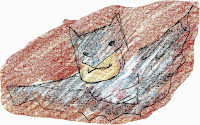久々の映画鑑賞。
バットマン新シリーズシリーズ、1作目。
評判のいい『ダークナイト』を見たいがための前段として『バットマン・ビギンズ』を見ました。
以下、ネタバレ含みます。
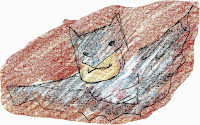 |
| BEGINS! |
クリストファー・ノーランはなぜ「ビギンズ」を描く必要があったのか
映画を観終わった後、このサブタイトル「begins」について、非常に納得しました。
これは「バットマン誕生物語」としての「begins」ではあるけれども、それ以上に新バットマン3作の「1作目」としう意味の「begins」でもあると思う。
つまり、クリストファー・ノーラン監督から
「みなさん、今までのバットマン像はいったん忘れてください。これから3作通して描く”バットマン”はこういうものなんです」
というメッセージが込められていると思います。
この映画で描かれているバットマンおよびその世界観はこれまでのバットマンと一線を画します。
これまでのバットマンを想定したまま次の「ダークナイト」「ダークナイトライジング」を見てしまうと、「???」となってしまうと思う。(見てないから想像だけど、たぶん間違いない)
だから、この「ビギンズ」で鑑賞者の頭の中をいったんリセットして、新バットマンの世界観をみんなで共有する意味合いが非常に強いように感じました。
もちろん、この映画単体としても面白かったです。
テーマは恐怖
僕の感じたこの映画のテーマは「恐怖」だと思います。
敵もバットマンも「恐怖」を武器にしている。
敵を一人一人こっそりやっつけていくバットマンはまるで「
プレデター」だ。どちらかというと悪者の手口だ。
また、悪者の破壊活動も「恐怖」を念頭に計画されている。
ただ単に街を破壊するだけならほかにも方法がある。だけど、あえて回りくどい方法をとっているのは、街中を「恐怖」で満たすことに重点を置いている。
バットマンも悪者も、恐怖を利用して理想を目指します。
重要なのは恐怖とどう対峙するか? だと思いました。
スパイダーマンとの比較
最近のアメコミ映画として、やっぱりスパイダーマンと比較してしまいます。
スパイダーマンとの違いとして、僕は2つの点があると思う。
違い1:超人の成り立ち
スパイダーマンは蜘蛛に刺されて特殊な力を得る。冴えない学生(だったっけ?)がいきなり超人的パワーを得ることによって人生ががらりと変わるというパターン。
突然得た力に普通の人が翻弄される苦悩を描いている。
一方バットマンは、身体的に何らかの超人的パワーがあるわけではない。彼は精神力と科学とトリックで超人になる。
それらを身に着けるため、子どものころのトラウマを執拗に克服しようとする主人公が描かれている。そのため、物語前半はかなり泥臭い。バットマンにたどり着くまで結構時間がかかる(それでも最初の方は展開が急ぎ足に感じたけど)。
どちらがいいというわけではないけど、同じヒーローものでも超人の成り立ちが全然違うので、テーマも全然違う。
違い2:スパイダーマンは「動」。バットマンは「静」。
スパイダーマンは「動」のイメージ。音も立てずにそーっと忍び寄る。
音はないけど、忍び寄るイメージが映像として思い浮かぶ。
「バレエ」的な動き。
バットマンは「静」のイメージ。気が付いたらそこにいる。
いつのまにそこにいるのか、どうやってそこにいたのか想像がつかない。
未知のもの、理解不可能なことに対する「恐怖」がここでも表現されている。
「能」的な動き(イメージだけど)
そういえば修業のシーンで師匠が「隠れるのではなく消える!」みたいなことを言ってた(正確じゃないけど)
僕は、どちらかというとバットマンのたたずまいというか、姿勢というかが大好きです。
あのマスクをかぶると、「バットマンは動じんなぁ」といっつも感心してしまいます。
世界観
バットマンのメインステージとなる「ゴッサムシティ」は、現実世界の一部として描かれている。
これまでのバットマンのゴッサムシティとは違い、かなり「現実的」だ。
バットマンのアイテムも近未来にありえそうなものだ。
恐怖とどう対峙するか? という人間的な部分をより濃く描くために、SF的な何でもありの要素を排除したんじゃないかなと思う。
この映画で一番SF的(アメコミ的?)なのは、ヒマラヤと忍者の組み合わせだと思う。
「なんでヒマラヤに忍者やねんwww」という突っ込みは「アメコミ」という枠で吸収可能な映画的ちっちゃな「ウソ」だと思います。
許容できない人もいるだろうけど、僕は「アメコミだからな」の一言で笑って許容できる範囲でした。
乗り越えるべきは父親
テーマとして「恐怖」というのはあるけど、もう一つ「父親を乗り越える」というテーマもあると思う。
偉大な父親の「負」の部分が自分や街に襲い掛かかる。(父親が残した会社の資金力や開発した兵器など。また、父親が作った街のシステムそのものが凶器として利用される。)
また、それによって、父親を象徴するビルが破壊されそうになる。
それに対して、父親の誇りを守り、街の破壊を阻止することことで、父親を乗り越える。
また、敵によって父が自分に残してくれた「居場所」は破壊されてしまう。
だけど、戦う術を身に着けた主人公は、自分で自分の居場所(基地)を再建することを誓う。
父親のトラウマのために父親の力で戦うのではなく、自らの意志で自らの力で戦うという決意の表れだと思います。
この「ビギンズ」の物語を通して主人公は父親から解放される。それこそが本当の「バットマン誕生」ではないだろうか?
父親の呪縛から解放されたバットマンが、次回作からどう戦っていくのか!?
『ダークナイト』。楽しみです。
あとがき
この映画を見るにあたって、「バットマン・リターンズ」でも「バットマン・フォーエバー」でもなく、正しく「バットマン・ビギンズ」をレンタルしてきてくれた妻に、この場を借りてお礼を言いたいと思います。
ありがとう。