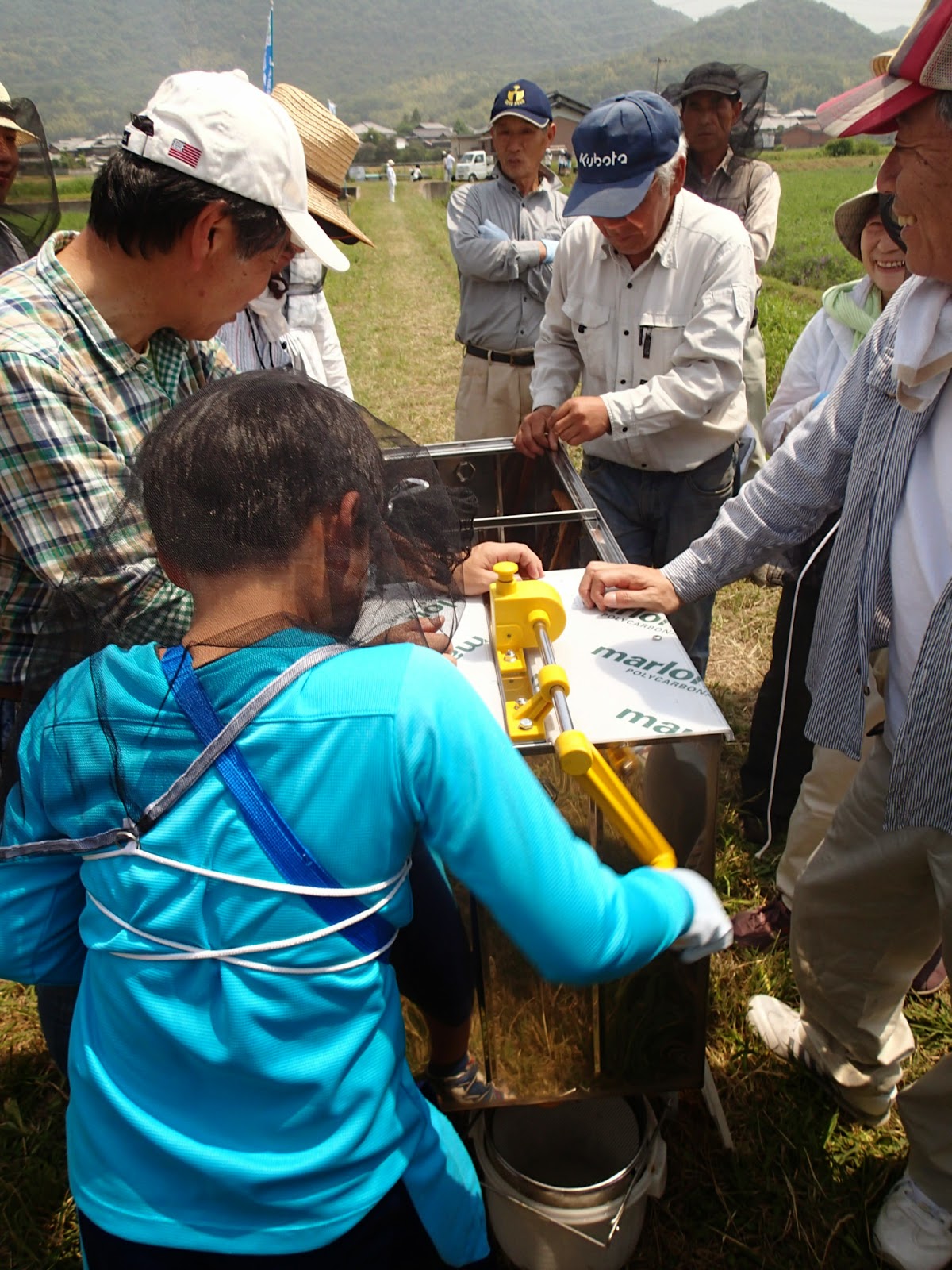読んだ。すべての話について感想を書くのは大変なので、とりあえず『ドライブ・マイ・カー』だけメモ。
ネタバレアリ。
村上 春樹
文藝春秋 (2014-04-18)
売り上げランキング: 97
『ドライブマイカー』
みさきとは何ものか
主人公家福は、女性には2種類いると考えている。
“いささか乱暴すぎるか、いささか慎重すぎるか、どちらかだ”
しかし、物語の中で出会う“みさき”は、このどちらかにも当てはまらない。
物語での冒頭に出てくる、家福の“女性論”に当てはまらないというこの事実は、とても重要な意味を持つと思う。
単純に異性として意識しない存在と言うだけではないと思う。
彼女は、家福にとって理解を超えた存在であり、人知を超えた存在であるといえる。
家福は処世術として、世の中をかなり偏見に満ちた目で眺めているように見える。
禍福は目の前のものをとりあえず便宜的に「こういうものだ」と仮定する。
もちろん家福自身も、100%その仮定が正しいと思っていないけど、そういう風に仮定して不都合は特にないし、その方が世界がわかりやすくなるからそうしている。
たとえば、“女性には2種類いる”とか、“〇〇村ではみんなポイ捨てをする”とか。
みさきの登場は、そんな家福を揺さぶる。そして物語が動きだす。
物語の中でみさきは、鶴の恩返しの鶴みたいな、人知を超えたものを与えるためにやってきたんだと思う。
盲点について
この物語は“盲点”が一つのテーマだと思う。
家福は、生きやすいように偏見を抱えて生きている。あまりにもそれに慣れすぎて、それが“盲点”となって、彼を苦しめている。
なぜ、彼の奥さんは“大したことのない”高槻と浮気をしなければならなかったのか。
物語の中で、家福は高槻のことをかなりけちょんけちょんに言っている。
家福は高槻のように愚かな振る舞いはしないかもしれない、だけど、家福は高槻のように正直な気のいい振る舞いもできない。
うまく言えないけど、心の奥底家福は高槻のことを羨ましく感じているように見える。
あんなふうに、正直に素直に生きていけたらいいのにと。
だけど、家福の生き方ではそれに気づくことができない。すでに家福は“高槻は愚かだ”という偏見を持っているため、“高槻の生き方が羨ましい”という気持ちは盲点となって見えない。
そういう盲点が、“妻の浮気”という別の形を持って具現化したんじゃないだろうか。
ある意味で、妻の浮気は“高槻のような(素直な)生き方を望んでいる家福自身”を気付かせるためのメタファーなんじゃないだろうか。
そんな気がする。
実在の土地、架空の土地
単行本化にあたって、『ドライブ・マイ・カー』に出てくる北海道の地名が、実在のものから架空のものに変えられた。
まえがきで
“テクニカルな処理によって問題がまずは円満に解決できてよかった”
とある。
テクニカルな処理によって何とかなる程度で使われてたんだと思うのも、なんだかアレだけど、実在の地名が使われた雑誌を読んだ時と、架空の地名になった単行本を読んだ時と、やっぱり少し印象が違ったので、その辺をメモ。
実在の地名の場合、それは揺るぎようもなく「この町だ」というものが存在する。もちろん、「そんな町聞いたことない」って言う場合もあるし、その場合はそれが実在するのか架空のものなのかすら判断できない。だけど、「実在するのに実在するかどうかわからないような町」という微妙な表現が成り立つ。
架空の地名の場合、その地名がいったいどういう町なのか、どれくらいの規模で、どの辺にあるのか、すべて想像の世界になる。もちろん文脈から判断することはできるけど、すべて読者(あるいは作者)の頭の中にだけ存在する町になる。「実在するかどうかもわからないような架空の町」を表現するのって結構難しいと思う。
と、まあ、かなり細かいニュアンスの違いはあると思うけど、「だだっ広いだけのパッとしない町」という意味においては確かに“テクニカルに処理できる程度の問題”だと思う。
と言うような話をしたら、雑誌掲載時に使われた実在する町に住んでいる人たちは怒るかもしれないけど、3分の2が森林と言われる日本において、「パッとしない」ことのない町がいったいどれだけあるだろうか。星の数ほどある「パッとしない町」の中から作者がそこを選んだのには、「みんな知らないけど、僕だけは知っている」という思い入れはやっぱりあるんじゃないだろうか。
そんな気がします。